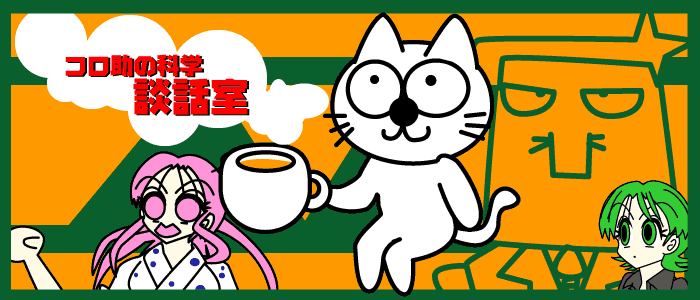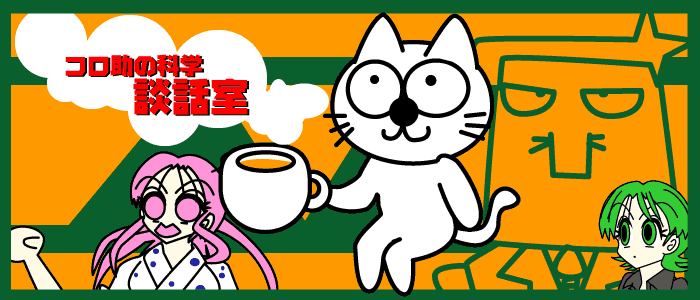|
 今回のコロ助の科学質問箱は数多くの疑問を 今回のコロ助の科学質問箱は数多くの疑問を
その場でさばいて いこうという形式でお送りします。
では、皆様の疑問に解答してくださる先生をご紹介いたします。
ロシア共和国、南ルビヤンカ大学複数学部授のミハイル・ スースロフ教授です。
|
 どうも。 どうも。
私がスースロフだ。
こちらは助手のタチアナ君だ。
|
 こんにちは助手です。 こんにちは助手です。
|
|
 よろしくお願いします。 よろしくお願いします。
ところで、スースロフ教授の専門の複数学というものは、
一体どういうものなのですか?
|
 んあ? んあ?
この国では複数学の説明からいちいちせんといかんのかね。
なんてことか。よくそれで経済大国などといえたものだね。
|
|
 す、すいません。何しろこちらでは聞いたこともないので… す、すいません。何しろこちらでは聞いたこともないので…
|
 ふんっ、まったく世話が焼ける。 ふんっ、まったく世話が焼ける。
タチアナ君、この極東の島国根性野郎に説明してやってくれ。
|
|
 ぐっ…。 ぐっ…。
|
 はい、複数学というのは、一以外のことを教える学問です。 はい、複数学というのは、一以外のことを教える学問です。
|
|
 は? は?
|
 つまり、2や3や4や5や6や7や8や9や10のことを取り扱うのです。 つまり、2や3や4や5や6や7や8や9や10のことを取り扱うのです。
|
|
 あの、それだけですか。 あの、それだけですか。
|
 11や12や13や14や15や16や17や18や19や20のことも研究します。 11や12や13や14や15や16や17や18や19や20のことも研究します。
|
 物分りの悪い女だな、君は!つまり一つしかないもの以外の 物分りの悪い女だな、君は!つまり一つしかないもの以外の
ことは すべて複数学の範囲なのだ!
世界で最も広いジャンルを網羅できる、 地上最強の学問なのだよ!
|
|
 21や22や23や24や25や26や27や28や29や30や 21や22や23や24や25や26や27や28や29や30や
|
|
 わかりましたわかりました。 わかりましたわかりました。
とりあえず時間もないことなので
質問に移らせていただきますよ。
こちらは、gori.shさんからの質問。
「カレーの美味しい食べ方を教えてください。」
とのことなんですが、先生のお国にカレーはありますか?
|
|
 馬鹿にしてもらっちゃ困るな。この世のことをすべて統括すると 馬鹿にしてもらっちゃ困るな。この世のことをすべて統括すると
いってもほとんど過言ではないのだよ複数学は。
|
|
 それはうかがいましたが。 それはうかがいましたが。
|
|
 で、そのカレーというのはうまいのかね。 で、そのカレーというのはうまいのかね。
|
|
 …すいません、そういうのは、自分の知らない言葉に …すいません、そういうのは、自分の知らない言葉に
であって、知ったかぶりをしたときの古典的なボケですが、
本当に食べ物の場合は成立しないんですが。
|
|
 ハッ! ハッ!
|
|
 笑いとばすなっ! 笑いとばすなっ!
|
|
 68や69や70や71や72や73や74や75や76や 68や69や70や71や72や73や74や75や76や
|
|
 お前も黙れっ! お前も黙れっ!
|
|
 まったく、わがロシアの文化のアネクドートを理解できん奴とはおちおち話もできんわ! まったく、わがロシアの文化のアネクドートを理解できん奴とはおちおち話もできんわ!
|
|
 どこに成治への風刺が含まれてるんだ。 どこに成治への風刺が含まれてるんだ。
まあそれはともかく、カレーのおいしい食べ方を教えて
いただきたいんですが。
|
|
 そんなものは空腹で食えばなんでもうまいだろう。 そんなものは空腹で食えばなんでもうまいだろう。
|
|
 …あの、あまりに当たり前のことで少々面食らってしまったんですが。 …あの、あまりに当たり前のことで少々面食らってしまったんですが。
|
|
 空腹を馬鹿にしちゃいかんよ。我がロシアのスーパーマーケットには常に調味料として空腹が売っているほどだよ。 空腹を馬鹿にしちゃいかんよ。我がロシアのスーパーマーケットには常に調味料として空腹が売っているほどだよ。
|
|
 そっちのほうがアネクドートぽいですが。 そっちのほうがアネクドートぽいですが。
|
|
 しかし、この極東の寂れた国、日本ではそういったものを入手するのも困難だろうから、特別に私が考案した方法を教えてやろう。ありがたく思え。 しかし、この極東の寂れた国、日本ではそういったものを入手するのも困難だろうから、特別に私が考案した方法を教えてやろう。ありがたく思え。
|
|
 ぐああああががが。 ぐああああががが。
|
|
 まず、カレーライスをどうやって食べる。 まず、カレーライスをどうやって食べる。
|
|
 それはまあスプーンでですか。 それはまあスプーンでですか。
|
|
 そこだよ。カレーライスを食べる人間の口に入るのは、 そこだよ。カレーライスを食べる人間の口に入るのは、
カレー、そしてライス、スプーンの三つだ。つまり、カレーライスの三分の一の味は、スプーンが決めるのだよ!だから、うまいスプーンを
開発すればどんなカレーライスでも確実においしく食べられるのだ!
|
|
 話がおかしいわっ! 話がおかしいわっ!
|
|
 それを実現するのがこの「味メッキ装置」だ。すでに新潟県の燕市・三条市に導入する交渉をしているのだ。 それを実現するのがこの「味メッキ装置」だ。すでに新潟県の燕市・三条市に導入する交渉をしているのだ。
|
|
 はい、もういちいちつっこんでると疲れそうなので はい、もういちいちつっこんでると疲れそうなので
さっさと次にいきます。
味噌煮込みアンパンさんのご質問、
「鏡の作り方を教えてたもれ。」とのことですが
|
|
 愛してタムレ? 愛してタムレ?
|
|
 さらっと流してください。 さらっと流してください。
|
|
 まあ鏡というのはだね、あれだよ。ありのままの物を映さないといけないわけだからな、いろいろと気を使うのだよ。 まあ鏡というのはだね、あれだよ。ありのままの物を映さないといけないわけだからな、いろいろと気を使うのだよ。
|
|
 そうですねえ、ゆがみや傷があったりしたらたいへんですからね。 そうですねえ、ゆがみや傷があったりしたらたいへんですからね。
|
|
 いや、そうじゃなくて、お客様以外の物を最初に映したらまずいだろう。 いや、そうじゃなくて、お客様以外の物を最初に映したらまずいだろう。
|
|
 …まずい…ですか? …まずい…ですか?
|
|
 たとえば君が靴下を買ったときに誰かがはいた靴下を売られたら腹が立つだろうが。 たとえば君が靴下を買ったときに誰かがはいた靴下を売られたら腹が立つだろうが。
|
|
 …それはそうですが…鏡は別に… …それはそうですが…鏡は別に…
|
|
 だから鏡は完全な闇の中で作られるのだよ。何しろ闇の中で作られるから、どうやって作っているかは職人にも見えないという寸法だ。 だから鏡は完全な闇の中で作られるのだよ。何しろ闇の中で作られるから、どうやって作っているかは職人にも見えないという寸法だ。
|
|
 それでよく鏡ができるなっ! それでよく鏡ができるなっ!
|
|
 手元が見えないものだから、鏡を作るつもりがアンパンやイージス艦やブリタニカ国際大百科事典なんかが出来上がってしまったりすることもあるのだよ。 手元が見えないものだから、鏡を作るつもりがアンパンやイージス艦やブリタニカ国際大百科事典なんかが出来上がってしまったりすることもあるのだよ。
|
|
 できるかあっ! できるかあっ!
|
|
 先生、これはゆうさんからいただいた質問です。 先生、これはゆうさんからいただいた質問です。
「何故シャボン玉は丸いのか?」
ということなんですが。
|
|
 丸いね、うむたしかにシャボン玉は丸いよ。なぜ丸いか。それは表面張力だよ。 丸いね、うむたしかにシャボン玉は丸いよ。なぜ丸いか。それは表面張力だよ。
|
|
 あ、普通ですね。 あ、普通ですね。
|
|
 液体には表面張力というものがあってだね、少しで表面積を 液体には表面張力というものがあってだね、少しで表面積を
少なくしようと球体になろうという性質があるのだよ。
|
|
 なるほど、それで液体が少なくて重力の影響を なるほど、それで液体が少なくて重力の影響を
あまり受けないのでシャボン玉は丸くなるのですね。
|
|
 と、いうのは、表向きの事情だ。 と、いうのは、表向きの事情だ。
|
|
 表向きっ? 表向きっ?
|
|
 そうなるまでにはシャボン玉内での複雑な暗闘があるのだよ。 そうなるまでにはシャボン玉内での複雑な暗闘があるのだよ。
はたして表面張力に逆らわずに丸くなるべきか、それとも、力に屈せず四角となるべきか。はたまたストローと同盟を組み、長くなるか…
|
|
 ハア… ハア…
|
|
 時には血が流れたこともあった。自分たちの理想を追求するために… 時には血が流れたこともあった。自分たちの理想を追求するために…
|
|
 シャボン玉が。 シャボン玉が。
|
|
 で、そんなこともあったな、と今ではすっかり丸くなった、というわけだよ。 で、そんなこともあったな、と今ではすっかり丸くなった、というわけだよ。
|
|
 人間的にかっ!!形の話しだっ! 人間的にかっ!!形の話しだっ!
|
|
 つぎはこちらです。杉山麻美さんの質問。 つぎはこちらです。杉山麻美さんの質問。
「標高が高くなると、太陽に近づくはずなのに、
寒くなるのはなぜですか?」
|
|
 ふん、少々標高が高いところなぞより、わが祖国ロシアのほうがよっぽど寒いわっ! ふん、少々標高が高いところなぞより、わが祖国ロシアのほうがよっぽど寒いわっ!
|
|
 そんな自慢をされても困りますが。 そんな自慢をされても困りますが。
|
|
 まず、太陽に近ければあたたかいというのは一種の誤解だな。 まず、太陽に近ければあたたかいというのは一種の誤解だな。
少々標高が高いぐらいで太陽の影響が変化するのであれば、
夜と昼の温度差はもっとあるぞ。何しろ地球の直径分も太陽から
遠ざかるのだからな。
|
|
 そういえばそうですね。 そういえばそうですね。
|
|
 だから、太陽のことはこの際忘れておこう。それ以外の事情によって気温というのは変わってくるのだ。 だから、太陽のことはこの際忘れておこう。それ以外の事情によって気温というのは変わってくるのだ。
|
|
 どんな事情でしょうか。 どんな事情でしょうか。
|
|
 標高が高いところというのは地上に比べて空気が薄いのだ。 標高が高いところというのは地上に比べて空気が薄いのだ。
薄いということはつまり、地上より気圧がはるかに低いということなのだ。
|
|
 なるほどそれで熱を保つことができないわけなのですね。 なるほどそれで熱を保つことができないわけなのですね。
|
|
 いやそんなことはどうでもいいので、空気のことも忘れてくれ。 いやそんなことはどうでもいいので、空気のことも忘れてくれ。
|
|
 お前が言ったんじゃねえかよ空気の話っ! お前が言ったんじゃねえかよ空気の話っ!
|
|
 黙れ。 黙れ。
で、標高の高いところは地面も少ないわけだ。地上に比べてな。
|
|
 ………。 ………。
|
|
 なんか言えっ! なんか言えっ!
|
|
 乗るだけ損だとわかってんだよっ! 乗るだけ損だとわかってんだよっ!
|
|
 黙れっ!黙れっ! 黙れっ!黙れっ!
|
|
 ……。 ……。
|
|
 なんか言えっ! なんか言えっ!
|
|
 やかましいわっ! やかましいわっ!
|
|
 よく言うだろう、「娘さんよく聞けよ、山男にはほれるなよ」と。 よく言うだろう、「娘さんよく聞けよ、山男にはほれるなよ」と。
|
|
 歌ですが。 歌ですが。
|
|
 山男は恋愛を拒絶する氷の心の持ち主、その上山食堂のおばちゃんや山トランペットを少年に買い与える老紳士などの心温まる人もいない山に温かさなどあるわけないだろうが! 山男は恋愛を拒絶する氷の心の持ち主、その上山食堂のおばちゃんや山トランペットを少年に買い与える老紳士などの心温まる人もいない山に温かさなどあるわけないだろうが!
|
|
 今のも忘れていいいんですかね。 今のも忘れていいいんですかね。
|
|
 があっ! があっ!
|
|
 では次ですが、 では次ですが、
「外国にある死海は人間が浮くけど、砂糖水だったら、人間は浮くのでしょうか?」と花井一成さんの質問です。
|
|
 どうなんですかねえ。 どうなんですかねえ。
|
|
 この地上には砂糖水の海というのは存在しない。だがもし、砂糖水の海というのがあったとすれば、それは糖尿病患者の尿でできたと考えるのが自然だろう。そんな海に浮きたいと本気で人間は思うことができるのかね?はなはだナンセンスといわざるをえないね。 この地上には砂糖水の海というのは存在しない。だがもし、砂糖水の海というのがあったとすれば、それは糖尿病患者の尿でできたと考えるのが自然だろう。そんな海に浮きたいと本気で人間は思うことができるのかね?はなはだナンセンスといわざるをえないね。
|
|
 砂糖水の話だっ! 砂糖水の話だっ!
|
|
 yapp2さんの質問。 yapp2さんの質問。
「紫外線が増加すると
なぜ植物にも影響が出るんですか?」
|
|
 紫外線というのは強い光なのだ。少々の細菌なら死に至らしめる。我々にとって小さくて見えない細菌も、植物にとっては小さないつくしむべき存在に見えているかもしれない。そういったものが命を奪われる姿を見て、心を痛めない植物がいるとすれば、それは植物ではない、鬼だ! 紫外線というのは強い光なのだ。少々の細菌なら死に至らしめる。我々にとって小さくて見えない細菌も、植物にとっては小さないつくしむべき存在に見えているかもしれない。そういったものが命を奪われる姿を見て、心を痛めない植物がいるとすれば、それは植物ではない、鬼だ!
|
|
 影響ってメンタル面かよっ! 影響ってメンタル面かよっ!
|
|
 まるこさんの質問は、「野菜を煮るときに砂糖を入れると野菜が軟らかくならないのはなぜですか?」 まるこさんの質問は、「野菜を煮るときに砂糖を入れると野菜が軟らかくならないのはなぜですか?」
|
|
 砂糖を入れると周りが砂糖水だ。 砂糖を入れると周りが砂糖水だ。
砂糖水といえば糖尿病患者の尿だ。
そんな中で野菜にリラックスしてやわらかくなれというのかね?
|
|
 尿はもういいっ! 尿はもういいっ!
|
|
 みかさんより、「実験でワインを凍らしたらシャーベットみたいになったのはどうしてですか?」 みかさんより、「実験でワインを凍らしたらシャーベットみたいになったのはどうしてですか?」
|
|
 ぶどう酒はキリストの血であるという。キリストは実はロシアで死んでいたという説はないからおそらく血は凍ったりしなかったんじゃないかね。 ぶどう酒はキリストの血であるという。キリストは実はロシアで死んでいたという説はないからおそらく血は凍ったりしなかったんじゃないかね。
|
|
 科学の話をしろっ!! 科学の話をしろっ!!
|
|
 桜庭裕久さんからは以下の二つの質問が。 桜庭裕久さんからは以下の二つの質問が。
(1)カーネーションを染めるのに食紅だと染まるが、服を染める染料だと色がつかないのは何故か。
(2)カーネーションを染めるのにはなんの原料を使用しているのか。
|
|
 つまり、カーネーションが染まる条件を考えれば二つの疑問は氷解するのだよ。カーネーションが染まるというのは、カーネーションの細胞組織の中に色素が定着するということだ。つまり、カーネーションの内部には一部の色素に対して家賃補助などの支援措置をとっているので、補助を受けられる条件があった色素は定着できるのではないかね。 つまり、カーネーションが染まる条件を考えれば二つの疑問は氷解するのだよ。カーネーションが染まるというのは、カーネーションの細胞組織の中に色素が定着するということだ。つまり、カーネーションの内部には一部の色素に対して家賃補助などの支援措置をとっているので、補助を受けられる条件があった色素は定着できるのではないかね。
|
|
 過疎対策でかよっ! 過疎対策でかよっ!
|
|
 はっちゃんさんの質問は「二酸化炭素が溶けている液体は炭酸飲料ですが、酸素や炭素などが溶けている液体はありますか?」 はっちゃんさんの質問は「二酸化炭素が溶けている液体は炭酸飲料ですが、酸素や炭素などが溶けている液体はありますか?」
|
|
 世の中で何でも溶かす物体があるとすればそれは水だ、という話もある。しかし酸素飲料や炭素飲料を見たことがない君たちには 世の中で何でも溶かす物体があるとすればそれは水だ、という話もある。しかし酸素飲料や炭素飲料を見たことがない君たちには
容易に想像はつかないだろう。君たちも大人になればわかる。わかるのだよ!
|
|
 逃げんなっ! 逃げんなっ!
|
|
 ゆきさんの質問。 ゆきさんの質問。
「液体(水・オレンジジュース・お茶など)を凍らせて、とかすと、もとの液体にどんな特徴のあるものが 溶けるのが早いですか。」
|
|
 とけやすさというのは、つまりその液体が溶ける温度になるのに とけやすさというのは、つまりその液体が溶ける温度になるのに
どれだけの時間がかかるかということなのだよ。
とける温度が高ければ早いし、またその液体がまわりの熱を集めやすければそれだけ早くもなる。つまり、とける温度が高い熱マニアの液体、ということだね。
|
|
 だんだんやる気が見られなくなってきたぞっ! だんだんやる気が見られなくなってきたぞっ!
|
|
 マヨリさんの質問「太陽の光は何色なのか?それに対して虹の色が出来ているのか?」 マヨリさんの質問「太陽の光は何色なのか?それに対して虹の色が出来ているのか?」
|
|
 太陽の光の色というのはつまり我々が見ている光の色だ。つまり…うーむ、沙羅双樹の花の色、だな。 太陽の光の色というのはつまり我々が見ている光の色だ。つまり…うーむ、沙羅双樹の花の色、だな。
|
|
 目腐ってんのかっ! 目腐ってんのかっ!
|
|
 ではでは、最後の質問です。 ではでは、最後の質問です。
|
|
 長々と続けてきましたがようやく最後の質問。皆様、夏休み期間にたくさん質問をいただきましてありがとうございます。そしてすいません。本当にすいません。 長々と続けてきましたがようやく最後の質問。皆様、夏休み期間にたくさん質問をいただきましてありがとうございます。そしてすいません。本当にすいません。
|
|
 ふん!土下座外交かっ! ふん!土下座外交かっ!
|
|
 お前のせいだっ!最後ぐらい気合入れて答えろっ! お前のせいだっ!最後ぐらい気合入れて答えろっ!
|
|
 いきまーす。ナホさんの質問。 いきまーす。ナホさんの質問。
「なぜ、生ものは、腐るとくさいの?」
|
|
 まあいきなり反論するようで悪いが、生ものじゃなくても腐ると臭いぞ。私は一度2年生の通信簿を腐らせたことがあったが、あれはかなりきたな。 まあいきなり反論するようで悪いが、生ものじゃなくても腐ると臭いぞ。私は一度2年生の通信簿を腐らせたことがあったが、あれはかなりきたな。
|
|
 そんなもん腐らすような事態になるかっ! そんなもん腐らすような事態になるかっ!
|
|
 ふん、ノーベル賞受賞者の2人に一人が通信簿を腐らせているという話を知らんのかね? ふん、ノーベル賞受賞者の2人に一人が通信簿を腐らせているという話を知らんのかね?
|
|
 知りたくもないわっ! 知りたくもないわっ!
|
|
 これを知るにはまず物が腐るということに着いて考える必要がある。物が腐るというのは、バクテリアなどによってその物質が分解されていく過程のことだ。大豆は腐ると納豆になり、鮒は飯の上で腐ると鮒寿司になり、ニシンは缶詰の中で腐るとシュールストレミングになり、ウミツバメがアザラシの腹の中で腐るとキビャックになるというのが身近な腐敗の例だな。 これを知るにはまず物が腐るということに着いて考える必要がある。物が腐るというのは、バクテリアなどによってその物質が分解されていく過程のことだ。大豆は腐ると納豆になり、鮒は飯の上で腐ると鮒寿司になり、ニシンは缶詰の中で腐るとシュールストレミングになり、ウミツバメがアザラシの腹の中で腐るとキビャックになるというのが身近な腐敗の例だな。
|
|
 普通の人は身近に置きたくないようなものばっかりだけど。 普通の人は身近に置きたくないようなものばっかりだけど。
|
|
 だが、これらの腐敗の過程は最後まで突き詰めると無臭になり、土に還る。つまり臭いは腐っている途中だということなのだ。物質が一番変わる時代、そう、腐るということは人間にとっての思春期と同じことなのだよ! だが、これらの腐敗の過程は最後まで突き詰めると無臭になり、土に還る。つまり臭いは腐っている途中だということなのだ。物質が一番変わる時代、そう、腐るということは人間にとっての思春期と同じことなのだよ!
|
|
 おなじかなあ。 おなじかなあ。
|
|
 青春が甘酸っぱい思い出であるように、腐ったものもすっぱいではないか! 青春が甘酸っぱい思い出であるように、腐ったものもすっぱいではないか!
|
|
 いや…それだけか…。 いや…それだけか…。
|
|
 運動部の部室のにおいも甘酸っぱいではないか! 運動部の部室のにおいも甘酸っぱいではないか!
|
|
 さわやかさのかけらもないなっ! さわやかさのかけらもないなっ!
|
|
 青春時代には、自分の中から湧き上がってくるものをもてあまして、暴走するもの!盗んだバイクで夜の校舎窓ガラス壊してまわるもの!つまり、そういった物なのだよ腐ったもののにおいというのは! 青春時代には、自分の中から湧き上がってくるものをもてあまして、暴走するもの!盗んだバイクで夜の校舎窓ガラス壊してまわるもの!つまり、そういった物なのだよ腐ったもののにおいというのは!
|
|
 腐敗臭を尾崎豊みたいに言うな! 腐敗臭を尾崎豊みたいに言うな!
|
|
 ではでは、今月のコロ助の科学談話室、これでお開きでーす。次回をお楽しみに! ではでは、今月のコロ助の科学談話室、これでお開きでーす。次回をお楽しみに!
|
|
 もうやらねえよっ!二度と来るんじゃねえぞ四角野郎! もうやらねえよっ!二度と来るんじゃねえぞ四角野郎!
|
|
 ふははははは!私が来なくても第二第三の私がやってきて、 ふははははは!私が来なくても第二第三の私がやってきて、
この談話室をひらくであろう!なにしろ私は複数学の世界的権威なのだ!見ろっ!
|
|
 えっ? えっ?
|
|
|
|
 うぎゃああああああああっ! うぎゃああああああああっ!
|
|
|